「毎月頑張って働いているのに、なぜかお金が貯まらない」
将来に対する漠然とした不安を抱えながら、この記事にたどり着いた人も多いのではないでしょうか。
わたし自身も社会人になるまでは貯金が苦手でした。
しかし、貯金を習慣化した結果、20代で資産1,000万円を達成することができました。
今回は、20代のリアルな平均貯蓄額を信頼できるデータに基づいて解説します。
20代の貯金はどれくらい?リアルな平均額
社会人になってまず気になるのが、「みんなはどれくらい貯金しているの?」という疑問ですよね。
まずは、国や金融機関が発表している信頼性の高いデータを見ていきましょう。
20代の平均年収・手取額はいくら?
国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、20代の平均年収は以下の通りです。
20~24歳:平均年収273万円
25~29歳:平均年収389万円
年収から税金や社会保険料が引かれた後の「手取り収入」は、年収の約8割と言われています。
たとえば、年収400万円なら手取りは約320万円(月26.6万円)、年収500万円なら手取りは約400万円(月33.3万円)が目安となります。
みんなの貯金額はいくら?20代の平均と中央値
続いて、実際にどれくらい貯金ができているのでしょうか?
世論調査の結果から20代の金融資産保有額をみていきましょう。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、20代の金融資産保有額は以下の通りです。
平均貯蓄額:280万円
中央貯蓄額:50万円
この平均値は、実家暮らしで潤沢な貯金がある人などが含まれているため、現実とは少し乖離があるかもしれません。
ここで注目したいのが「中央値」です。
中央値とは、データを小さい順に並べたときにちょうど真ん中に位置する値のことです。
つまり、20代で貯金が50万円以上ある人は全体の約半分(上澄み層)ということになります。
これから貯金に励みたいと考えている方は遠い目標を設定するのではなく、中央値を最初の目標にしてみるとよいでしょう。
ただし、X(旧Twitter)には20代で金融資産1,000万円以上の方も見受けられるので、まずはできる範囲からはじめてみるのが良いと考えます。
貯金に成功する人が実践していること
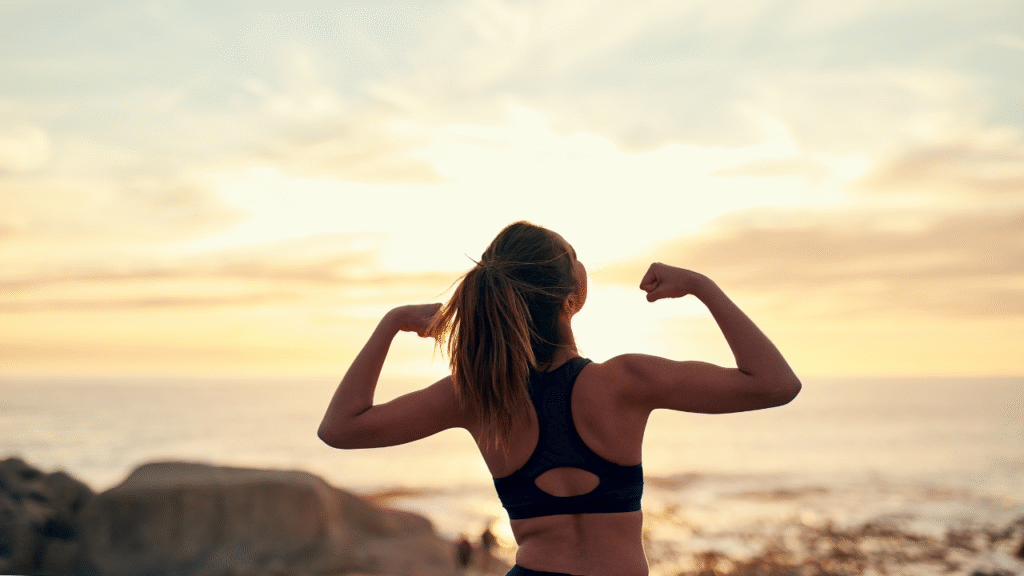
ここからは、実際に貯金に成功している人が実践している、誰でもできる貯金のコツをご紹介します。
結論:手取りの20%を貯金に回しましょう!
わたしが資産形成を加速させるきっかけとなったのは、本多静六(ほんだせいろく)という人物が書いた「私の財産告白」という書籍です。
本田清六は確実に貯蓄する方法として、「収入の四分の一天引き法(手取り20%)」を実践していました。
貧乏に強いられてやむを得ず生活をつめるのではなく、自発的、積極的に勤倹貯蓄につとめて、逆に貧乏を圧倒するのでなければならぬ
本田 清六
たとえば、手取りが月26.6万円なら5.3万円、手取り月33.3万円なら6.6万円が貯金の目安です。いわゆる先取り貯金を習慣化することで、着実に貯金が増えていくのを実感できると思います!
貯金が続く3つのコツとは!?
先取り貯金で自動化する
貯金が苦手な人が陥りがちなのが、「余った分を貯金しよう」という考え方。これではいつまで経ってもお金は貯まりません。成功の秘訣は、給料が入ったらすぐに貯金する「先取り貯金」です。
固定費を見直す
通信費:大手キャリアから格安SIMに乗り換える(ahamoやLINEMOなど)
サブスクリプション:動画配信アプリやゲームへの課金がないかチェックしましょう。
キャッシュレス決済を活用
キャッシュレス決済を利用することで、家計管理と節約が同時にできます。
例えば、クレジットカードやQRコード決済などポイント還元率が高いものをメインで使う。そのほか、家計簿アプリを使えば、お金の出入りが「可視化」されます。
私が20代で資産1,000万円を貯めた具体的な方法とマインド

ここからは、わたしの体験談をお伝えします。
わたしは20代で資産1,000万円を達成することができました。特別な才能があったわけではありません。ただシンプルな考え方を実践しただけです。
(1)スタートは「手取り20%貯金」から
私が貯金を始めたきっかけは、本多静六の「四分の一貯金法」です。
彼は「給料の4分の1を貯金し、残りの4分の3で生活せよ」と説きました。
これを参考に、社会人1年目の頃から無理のない手取りの20%貯金からスタートしました。
本多静六の時代と違ったのは、NISA制度があったことです。
年金2,000万円問題という話題はありませんでしたが、毎月の給料から最初に投資分を考慮し、残りで生活する。このシンプルなルールを守り続けたことで、貯金は着実に増えていきました。
(2)貯金を加速させた「お金の仕組み化」
貯金やNISAによる積立が軌道に乗ってからは、さらに貯金を加速させる「ボーナス」の使い道をより絞っていきました。
貯金が自動的に貯まるように努力を続けた結果、普段の生活費の3ヶ月分の貯金が常時口座にある状態へ。
そこからは手取りの35%を投資信託の積立NISAに回すようにしました。
これを実現するためのコツは、家計簿アプリで「見える化」することです。
使ったお金を毎日記録し、月末には何にお金を使ったかを負担のない範囲で分析しました。
無駄なサブスクや保険の解約などを減らすことから始めてみましょう!

当時は同級生の誘いでドル建ての保険に加入していました。しかし、お金の勉強すればするほど資産形成にお金を捻出する優先度が高いという考えに至り、友人には悪い思いながら解約しました。
(3)貯金だけが全てじゃない!相談して結婚式も開催できた!
本記事のような貯金に関するブログ記事をみた方の中の多くは、「貯金のためにお金を使わない」ような変人と見られることもあるでしょう。
しかし、わたしはときに高価なカメラの購入や国内旅行など時には派手にお金を使うこともあります。
この「メリハリ」が、貯金を続けるモチベーションになっています。
例えば、妻との結婚式も開催し、数百万単位のお金を支払いました。
こうしたライフイベントでは、できるだけケチにならないようにしています。
お金を使うことで、仕事や日々の生活に対する満足度が上がり、より頑張ろうと思えるでしょう。
(4)家庭を持つことで貯金への意識が変わる
家庭を持つことで貯金に対する考え方が大きく変わりました。
それまでは自分のためだった貯金が、妻や将来の子どものためになりつつあります。
具体的には妻と貯蓄や収入を共有し、お互いのライフプランを描いて、将来必要なお金を逆算するようになりました。
これがきっかけで、今では手取りの35%以上を、老後資金や教育資金として資産運用に回しています。家族の幸せを最優先に考えることで、より堅実で長期的な視点を持つことができました。
まとめ
本記事では、20代の貯金は「知識」よりも「習慣」が重要であることをお伝えしました。
20代の貯蓄額は平均280万円、中央値は50万円という調査結果こそありますが、20代後半では貯金習慣があるか否かで大きく差が開きます。
お金を貯めることは、将来の選択肢を増やすことにつながります。
今日からあなたも「貯金できる人」になるための第一歩を踏み出しましょう!

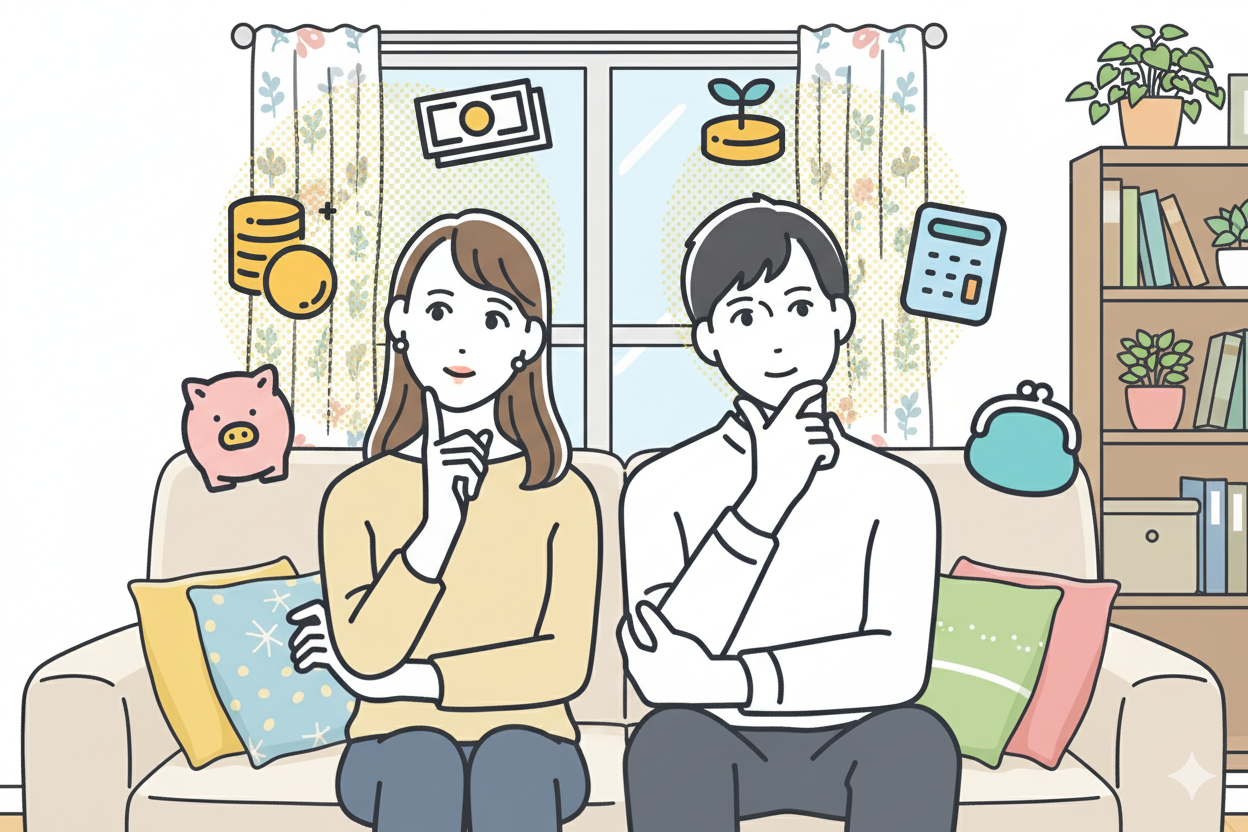


コメント